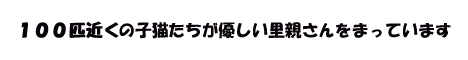(参照用)
「よって、この補正は同法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により上記結論のとおり決定する」
⇒
"Therefore, this amendment violates the stipulations of Japanese Patent Law, Article 126, Paragraph 5 applied mutatis mutandis to Japanese Patent Law, Article 17bis(bisは上付き) , Paragraph 5, and thus is ruled according to the above-mentioned conclusion under the stipulations of Japanese Patent Law, Article 53, Paragraph 1"
以下、審査基準から(第3部、第3節、4.3.4、4.4とか)。
「請求項の限定的縮減」 ⇒ "Restriction of Claim(s)"
「発明特定事項を限定する補正」 ⇒ "the amendment for restricting a matter specifying the invention"
「独立して特許可能」 ⇒ "independently patentable"
「第17 条の2 第5 項第2 号に該当する補正と認められても、補正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が特許可能なものでなければならない。」
⇒
"Notwithstanding the amendment being deemed as falling under Article 17bis(5)(ii), the invention specify by the matters stated in the amended claim shall be patentable."
「この要件が課されるのは限定的減縮に相当する補正がなされた請求項のみであり、これに相当しない「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」のみの補正がなされた請求項及び補正されていない請求項については、独立して特許を受けることができない理由が存在する場合において、それを理由として補正を却下してはならない。」
⇒
"This requirement is applied only to claim(s) which was amended to be restricted. The claim(s) which was amended solely in terms of "the correction of errors in the description" or "the clarification of an ambiguous description" as well as claim(s) that has not been amended must not be refused by the reason that they cannot independently be granted patents."
「独立して特許可能かどうかについて適用される条文は、第29 条、第29 条の2、第32 条、第36 条第4項第1 号又は第6 項(第4 号は除く)、及び第39 条第1 項から第4 項までとする。その他の取扱いは「第Ⅸ部 審査の進め方 第2 節 各論」の6.2.3 による。」
⇒
"Patent Act Articles 29, 29bis, 32, 36(4)(i) or (6) (except (iv)), and 39 (1) to (4) are applied with respect to the requirements of independently patentable. The other handling shall follow "Part IX: Procedure of Examination Section 2” 6.2.3."
「最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」
⇒
"Amendment of Claims after Final Notice of Reasons for Refusal"
(とりあえず審査基準の英語版には final と書いてますが、どこかで、これは penultimate なんじゃないか?っていう話も聞いたことあります。)
あ、ちなみに、私は上記の対訳等、当サイトでご紹介させて頂きましたものが全て正しいと思っているわけではありません。あくまでも参照用です。特許庁が出しているものであっても、正しいからここでご紹介しているというわけではありません。念のため。
お気楽な特許翻訳者が、害の(なるべく)無い与太話(Prolefeed)をお気楽に書いているページです。 難しいことは良く分からないけれど、とりあえず特許関連の日本語⇒英語、英語⇒日本語の翻訳をやっている、特許業界の雰囲気にあまり馴染めていないけどとりあえず業界にいます、みたいな人が書いてます。
2010年10月3日日曜日
2010年7月4日日曜日
co-owned; co-pending; commonly assigned; incorporated herein by reference...; provisional application; non-provisional application
外国からのパリ経由の出願またはPCTの国内移行ででてくる、例えば、
.....such as those disclosed in co-owned, co-pending, and commonly assigned U.S. Patent Application No. ##/###,###, entitled "xxx xxx xxx," which is hereby incorporated by reference.....
co-owned は、「共有の」とか「共同」とかでいいのかな。恐らく、solo application に対する co-owned application (たぶん共同研究の結果としての共同出願を示唆しているんだと思う)という意っぽいので。
co-pending は、「同時係属中」、「同時係属の」って感じでしょうか。
commonly assigned は、他所のところから参照(汗)したのですが、「本発明の譲受人に譲渡された」だそうです。若干意味が取り辛いかもですが、要は、その出願(特許)の権利自体が、個々人としての発明者から、その人の属する企業なりへと譲渡されていますよ、って感じの意味っぽいです。なので、恐らく、発明者の立場が比較的強いものとして扱われている米国内の出願にこういった表現が多いのかなっと思います。(ちなみに、この業界の法律文書的な局面で、Assignment といったら、ほぼ間違いなく譲渡証書のことだったりします。)
hereby incorporated herein by reference ...っていうのは頻出するので、是非憶えておきたいところなのですが、定訳ってあるんですかねぇ・・・よく外注さんなんかが「ここに組み込まれる」とかって訳出されてたりするのですが、できれば「引用(参照)することにより本明細書中に援用される」くらいに訳出してもいいんじゃないかと思ったりします。
ついでにちなみに、
provisional application は、米国特有の出願方法で、訳は、「仮出願」。日本からだと、基礎出願を日本にしたパリだとかPCTだとかじゃなくて、いきなり基礎から米国にするときなんかに、このルートを使ったりするみたいです。ちなみにとりあえず日本語で米国出願が出しちゃえるらしい(英訳はその後の数ヶ月でしなきゃなりませんが)ので、とりあえず出願日をすぐにゲットできる制度みたいです。そしてその後に本出願(non-provisional application)を行うっていう手筈になると。
って、偉そうに書いてても、この程度の知識で翻訳してるとかバレたら、、、(苦)とりあえず用語リマインダー。。。
2010年4月27日火曜日
コンピュータ・ソフトウェア関連発明 拒絶理由メモ
Examination Guidelines for Computer Software Related Invention
VIII. Examination Guidelines for Inventions in Specific Fields
Chapter 1. Computer Related Invention
人為的取決め ⇒ artificial arrangement
(II. Requirements for Patentability, 2.2 Actual Procedure for Judgement)
自然法則を利用した技術的思想の創作 ⇒ a creation of technical ideas utilizing natural laws
(II. Requirements for Patentability, 2.2 Actual Procedure for Judgement)
※特許庁のprovisional versionでの「自然法則」の訳語(natural laws)はネイティブ的にはちょっと微妙みたい。MPEPのほうでは、laws of nature の表現を使っているので、こっちのほうが良いかも。。
ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている ⇒ information processing by software is concretely realized using hardware resources
(II. Requirements for Patentability, 2. Statutory Invention)
ついでにこれらも・・・
平成9年(行ケ)第206号(東京高判平成11年5月26日判決言渡 ⇒ Heisei 9 (line ケ) No. 206 (Tokyo High Court Ruling as of May 26, Heisei 11
請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。(第I部第1章2.2.2.1(3)参照) ⇒ Inventions claimed as "shi-su-te-mu" (Japanese pronunciation of "system") or "hoshiki" (Japanese translation of "system") is deemed to be a product inevntion (see Guidelines, Part I, Chapter 1.1.2.2.2.1 (I) (3))
発明であること ⇒ statutory invention
組み合わせや適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合は、特段の事情(顕著な技術的効果等)がない限り、進歩性は否定される。 ⇒ so that when there is no technical difficulty (blocking factor) for the combination and the application, the inventive step is not affirmatively inferred without a special condition (such as remarkable advantageous technical effect).
(II. Requirements for Patentability, 3. Inventive Step (Nonobviousness))
2010年4月12日月曜日
2010年3月17日水曜日
In the context of the invention, the basic additives used may be alkali metal hydroxides such as lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, alkali metal carbonates or alkali metal hydrogencarbonates such as lithium carbonate, sodium carbonate, potassium carbonate or caesium carbonate, alkaline earth metal hydroxides such as magnesium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide or strontium hydroxide, alkaline earth metal carbonates such as magnesium carbonate, calcium carbonate or barium carbonate, ammonia, aliphatic alkylamines, e.g. mono-, di- or trialkylamines with optionally substituted Ci-C2o~alkyl radicals, such as methylamine, dimethylamine, trimethylamine, ethylamine, diethyl- amine, triethylamine, ethanolamine, dimethyl- ethanolamine or triethanolamine
本発明に関しては、使用される塩基性添加剤は、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムまたは炭酸セシウムなどのアルカリ金属炭酸塩またはアルカリ金属炭酸水素塩、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウムまたは水酸化ストロンチウムなどのアルカリ土類金属水酸化物、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウムまたは炭酸バリウムなどのアルカリ土類金属炭酸塩、アンモニア、脂肪族アルキルアミン、例えばメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、エタノールアミン、ジメチルエタノールアミンまたはトリエタノールアミンなどの、任意に置換されたC1~C20-アルキルラジカルを有するモノ-、ジ-またはトリアルキルアミンであってもよい。
2010年3月3日水曜日
発明特定事項 特別な技術的特徴
特許庁からの拒絶理由通知などで見かける表現。
(Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part I, Chapter 2, Section 4.2)
"matter(s) specifying the invention"
とか、
"matter(s) specifying the claimed invention"
これでとりあえず問題なし。
「特別な技術的特徴」は、
"special technical feature"
だそうな。特許庁審査官から直接聞いたのでアレですが、庁内ではこれをSTF、STFって呼んでるから間違いないよとのこと。。
「発明特定事項」 は、審査基準の英語版にもあるように
(特許・実用新案 審査基準 第I部第2章4.2あたり)
"matter(s) specifying the invention"
とか、
"matter(s) specifying the claimed invention"
これでとりあえず問題なし。
「特別な技術的特徴」は、
"special technical feature"
だそうな。特許庁審査官から直接聞いたのでアレですが、庁内ではこれをSTF、STFって呼んでるから間違いないよとのこと。。
2010年2月10日水曜日
独立特許要件
独立特許要件ってなにかと。
検索しても定訳がないみたいなので、特許庁が出してる審査基準の英語版(ベータ版)の対応箇所をみてみると・・・
requirements for independent patentability
めちゃくちゃそのまま。
ちなみに、特許庁の別ページの前置審査のところでは、
「独立特許要件:第29条、第29条の2、第32条、第36条、第39条をさす。」
ですって。文脈ごとに具体的に訳し分けたほうがよさそうだし、というか、何も考えずに上の訳だけ当てはめたりすると、海外のクライアントだって意味分からないような気もする・・・
といいつつも、仮に、勝手に手心加えて技術者に返したら、たぶん技術者は気分悪いだろうし。
ltoreq and gtoreq
ltoreq - less than or equal,
gtoreq - greater than or equal
ということで、省略みたい。
明細書なら、≧ と、 ≦ に置き換えてOKかな。
登録:
投稿 (Atom)